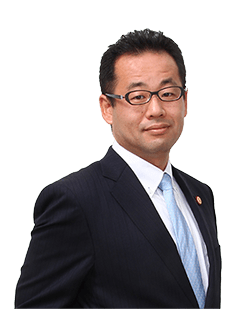大学との共同研究の際、途中でもめたり、時には破談になったり・・・
結局損するのは、大学ではなく企業側となります。
今回は「大学との共同研究で気を付けたい”5つ”のこと」について述べたいと思います。
弊所でも共同研究の契約書のチェックや交渉(またはその立ち合い)を行う場合がありますが、
知的財産の関係では、
研究成果の帰属
共同出願の取り扱い
秘密保持(成果物の発表含め)
が特に重要になります。
※実際には、他条項へ影響が及ぶ場合もあるため、全体的なチェックが必要になります。
1 研究成果の帰属
共同研究を通してできた知的財産(アイデア、技術等)は、
大学のもの?
企業のもの?
両社の共有物?
といった取り決めを行います。
この取り決めを、成果物ができた後に行う場合、
成果物利用する側(つまり企業側)の交渉力が下がってしまいます。
※ その理由は「ルパン三世と不二子ちゃん」の関係です。
ピンとこない方は、過去のブログ記事 特許出願に関する誤解 をご参照ください。
したがいまして、
こちら側に交渉力があるときに契約をまとめてしまう!
これが交渉のセオリーです。
大学との交渉の場合には、大学の研究費は企業負担となるため、
「大学側が研究費が欲しいなぁとおもうとき」
つまり、申し込み時に行うのがセオリーです。
2 共同出願の取り扱い
成果物に関する特許出願。
成果物が大学との共有物の場合、
大学との共同出願となるケースが多いのですが、
出願に関する費用は企業もち・・・
となるケースが多いです。
費用が企業もちなら、出願の持ち分は企業単独がイーブンでは?
という考えもありますがが・・・
ここは、
大学の協力なしには、成果物はできなかった
大学の名前を実績として使いたい! 等
別の理由もありますので、最終的には、事業戦略上のトレードオフとなります。
3 秘密保持(成果物の発表含め)
成果物の中には、
(企業側として)ブラックボックスにしたく特許出願をしない!
というものもあります。
一方、
大学としては成果を論文発表したい!
ここで利害が対立します。
秘密保持(成果物の発表含め)という条項は、この利害調整の役割を果たします。
要点としては、
発表前の事前承諾
発表内容の時期・内容・方法などの協議の機会の確保
となります。
気を付けたいポイントとしては
実は、もう二つあります。
それは、

信頼関係の構築と出口戦略です。
4 信頼関係の構築
信頼関係の構築に大きく影響するものが、
大学(組織として)のスタンスと教授のスタンスです。
前者は組織なので、ポリシーの確認でよいと思いますが、後者は個人。
ポリシーとキャラクターが混在するため、そのジャッジが難しいところ・・・です。
契約前の打ち合わせで、よく観察したほうが良いでしょう。
また、ビジネスセンス(WIN-WINの構築)を感じられない教授とは、距離を置いたほうが良いです。
5 出口戦略を見失わない
共同研究の目的が、単なる技術開発であればよいのですが、
そこにビジネスが絡むのであれば、
(1)技術開発の成果物を自社ビジネスにどう関わらせるか?
(2)共同研究契約書の条項が自社ビジネスにとって障害とならないかどうか?
について検討が必要でしょう。
共同研究契約書があまり修正ができないと判断した場合には、
共同研究を見送る、または、共同研究のテーマを変更する(いわゆるプランB)ことも必要になります。
また、大学とのコネクションづくりや、共同研究について実績作りでよい場合には、
共同研究のテーマを、自社の大切な技術ではなく、そうではない技術について変更したほうが良い場合もあります。
打ち合わせを重ねるたびに、契約書の内容や相手のポリシーやキャラクターに振り回されることがありますが、
共同研究における自社出口戦略を見失ってはなりません。
まとめ「大学との共同研究で気を付けたいこと」
1 研究成果の分担
アイデアはだれのもの?
自社のものなのか?他社の物なのか?それとも共有の場合なのか?
それぞれについて、自己実施や実施の義務、不実施保証についてもチェックが必要です。
2 共同出願の取り扱い
権利取得にかかる費用は誰が負担する?
権利の持ち分はどうなる?
負担と持ち分とのバランスはイーブンになっているか?
3 秘密保持(成果物の発表含め)
発表前の事前承諾や、発表内容の時期・内容・方法などの協議の機会の確保が必要になります。
4 信頼関係の構築
大学については、ポリシーの面からジャッジ可能。
教授については、ポリシーとキャラクターの混在につき、ジャッジが難しいケースもあります。
5 出口戦略を見失わない
共同研究に対する自社の目的について、ブレないことが何よりも大切です。
「成果物を自社ビジネスに結びつける」場合(プランA)と
「共同研究の実績作りにする」場合(プランB)とでは、研究テーマも契約書の内容も変わってきます。
相手方と打ち合わせする前に、専門家の意見を聞きながら出口戦略のプランA・プランBを用意したほうが良いと思います。
何かのご参考になれば幸いです。

かめやま特許商標事務所
弁理士 亀山 夏樹